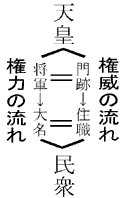 丂偳偙傑偱傕擔杮偼恄崙偱偁傞偺偱偡丅偩偐傜僉儕僔僞儞偑擖偭偰偒偰擔杮偺柉廜傪慡偰僉儕僔僞儞偵偟偰偟傑偭偰丄恄崙傪扗偄庢偭偰偟傑偆偺偱偼側偄偐偲偄偆嫲傟偺拞偐傜丄嵔崙傕偟帥惪惂搙傪揙掙偟偨丅柉廜偑僉儕僔僞儞偵側傜側偄傛偆偵娔帇偟偰偄偭偨偺偑丄帥惪惂搙偱偁傝抙壠惂搙偱偡丅帥惪惂搙丄抙壠惂搙偼暓嫵偱偡偑丄崻杮偼恄崙傪慜採偵偟偰偄傞傢偗偱偡丅偦偆偄偆帥惪惂搙傪晍偒側偑傜丄慡懱偲偟偰偼偙偆偄偆峔憿偵側傝傑偡丅乽揤峜乗彨孯乗戝柤乿偲偄偆尃椡偺棳傟偱柉廜傪摑帯偟偰偄偔偲偄偔偙偲偑偁傝傑偡丅偦偺尃椡偺棳傟偩偗偱偼柉廜傪墴偝偊偒傟側偄丅偱偡偐傜乽揤峜劅栧愓乗廧怑乿偲偄偆尃埿偺棳傟偱柉廜傪摑帯偡傞偲偄偆偙偲偑偁傝傑偟偨丅偙偆偄偆峔憿偑丄峕屗帪戙偑嶰昐擭娫懕偄偨崻杮偵側傞傢偗偱偡丅偙偺帪偵栧愓傪尃埿晅偗傞偺偑揤峜偵側傝傑偡丅彨孯偲偄偭偰傕丄揤峜偺彸擣偺拞偱偼偠傔偰彨孯偲偄偆偙偲偱偡丅揤峜偵傛偭偰尃埿偑棤懪偪偝傟偰偄傞傢偗偱偡丅尃埿丄尃椡傪棤懪偪偟偰偄偔愨懳揑側傕偺偲偟偰揤峜偼婡擻偟偰偄偨傢偗偱偡丅峕屗帪戙偺帥惪惂搙丄暓嫵惌嶔偲偄偆偺偼堦斣崻杮偵揤峜偺愨懳揑側尃埿傪棫偰偰偲偄偆偙偲偵側傝傑偡丅
丂偳偙傑偱傕擔杮偼恄崙偱偁傞偺偱偡丅偩偐傜僉儕僔僞儞偑擖偭偰偒偰擔杮偺柉廜傪慡偰僉儕僔僞儞偵偟偰偟傑偭偰丄恄崙傪扗偄庢偭偰偟傑偆偺偱偼側偄偐偲偄偆嫲傟偺拞偐傜丄嵔崙傕偟帥惪惂搙傪揙掙偟偨丅柉廜偑僉儕僔僞儞偵側傜側偄傛偆偵娔帇偟偰偄偭偨偺偑丄帥惪惂搙偱偁傝抙壠惂搙偱偡丅帥惪惂搙丄抙壠惂搙偼暓嫵偱偡偑丄崻杮偼恄崙傪慜採偵偟偰偄傞傢偗偱偡丅偦偆偄偆帥惪惂搙傪晍偒側偑傜丄慡懱偲偟偰偼偙偆偄偆峔憿偵側傝傑偡丅乽揤峜乗彨孯乗戝柤乿偲偄偆尃椡偺棳傟偱柉廜傪摑帯偟偰偄偔偲偄偔偙偲偑偁傝傑偡丅偦偺尃椡偺棳傟偩偗偱偼柉廜傪墴偝偊偒傟側偄丅偱偡偐傜乽揤峜劅栧愓乗廧怑乿偲偄偆尃埿偺棳傟偱柉廜傪摑帯偡傞偲偄偆偙偲偑偁傝傑偟偨丅偙偆偄偆峔憿偑丄峕屗帪戙偑嶰昐擭娫懕偄偨崻杮偵側傞傢偗偱偡丅偙偺帪偵栧愓傪尃埿晅偗傞偺偑揤峜偵側傝傑偡丅彨孯偲偄偭偰傕丄揤峜偺彸擣偺拞偱偼偠傔偰彨孯偲偄偆偙偲偱偡丅揤峜偵傛偭偰尃埿偑棤懪偪偝傟偰偄傞傢偗偱偡丅尃埿丄尃椡傪棤懪偪偟偰偄偔愨懳揑側傕偺偲偟偰揤峜偼婡擻偟偰偄偨傢偗偱偡丅峕屗帪戙偺帥惪惂搙丄暓嫵惌嶔偲偄偆偺偼堦斣崻杮偵揤峜偺愨懳揑側尃埿傪棫偰偰偲偄偆偙偲偵側傝傑偡丅恀廆偺嫵媊偼峜朄傪曭懻偟偰惉棫偣傞擔杮暓嫵偺惈奿傪偦側偊偨傞傕偺偱偁傞丅偲偁傝傑偡丅偙偙偵乽峜朄傪曭懻偟偰惉棫偣傞擔杮暓嫵乿偲偁傝傑偡丅
恀廆嫵搆偨傞傕偺偼丄奺帺偑帺屓偺怑愑傪捠偟偰戝惌傪梼巀偟偨偰傑偮傝丄戝屼怱傪曭懻偟恇柉摴傪慡偆偡傞偙偲偑愨懳偺摴偱偁傞偲丅乽戝惌傪梼巀乿偲偐乽戝屼怱傪曭懻偟乿偲偄偆偙偲偑偼偭偒傝偲尵傢傟偰偄傞傢偗偱偡丅旕忢帠懺偵側偭偰偒偨帪丄抧曽偺廧怑傕偳偺傛偆偵懳墳偟偰傛偄偺偐暘偐傜側偄丅偦偆偄偆偙偲偱丄杮婅帥偐傜乽崙懱娤擮偲恀廆嫵媊乿偲偄偆偐偨偪偱丄忣曬偑棳傟偰偔傞傢偗偱偡丅偦偙偱丄乽恀廆嫵搆偨傞傕偺偼丄奺帺偑帺屓偺怑愑傪捠偟偰懱惂傪梼巀偟偨偰傑偮傝丄戝屼怱傪曭懻偟恇柉摴傪慡偆偡傞偙偲偑愨懳偺摴乿偩偲丄偦偆偄偆払偟偑偁傞傢偗偱偡丅偦偟偰偙偺拞偱丄
揤峜婣堦偲偄偆偙偲偑孞傝曉偟尵傢傟偰偄傑偡丅揤峜偵婣堦偡傞偙偲偑崻杮偱偁傞偲丅堦偵婣偡傋偒偼揤峜偱偁傞偲丅偙偺乽恀廆偺嫵媊乿偲偄偆傕偺偑塱墦側傜偽丄尰嵼偱傕偦偆側偭偰偟傑偄傑偡丅揤峜婣堦偱偁偭偰栱懮婣堦偱偼側偄丅堦偵婣偡傋偒偼揤峜偱偁偭偰丄栱懮偱偼側偄丅栱懮偼婣埶偩偲丅偱偡偐傜丄垻栱懮擛棃偵婣埶偟傛偆偲丄庍夀擛棃偵婣埶偟傛偆偲丄戝擔擛棃偵婣埶偟傛偆偲丄偦傟偼揤峜婣堦偲偄偆偙偲偑崻杮偵偁偭偨忋偱偺偙偲偱偁傞偲偄偆偙偲偱偡丅恀廆嫵媊偺棟夝傪丄偙偆偄偆偐偨偪偱忣曬偲偟偰慡崙偵棳偡傢偗偱偡丅